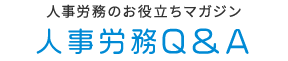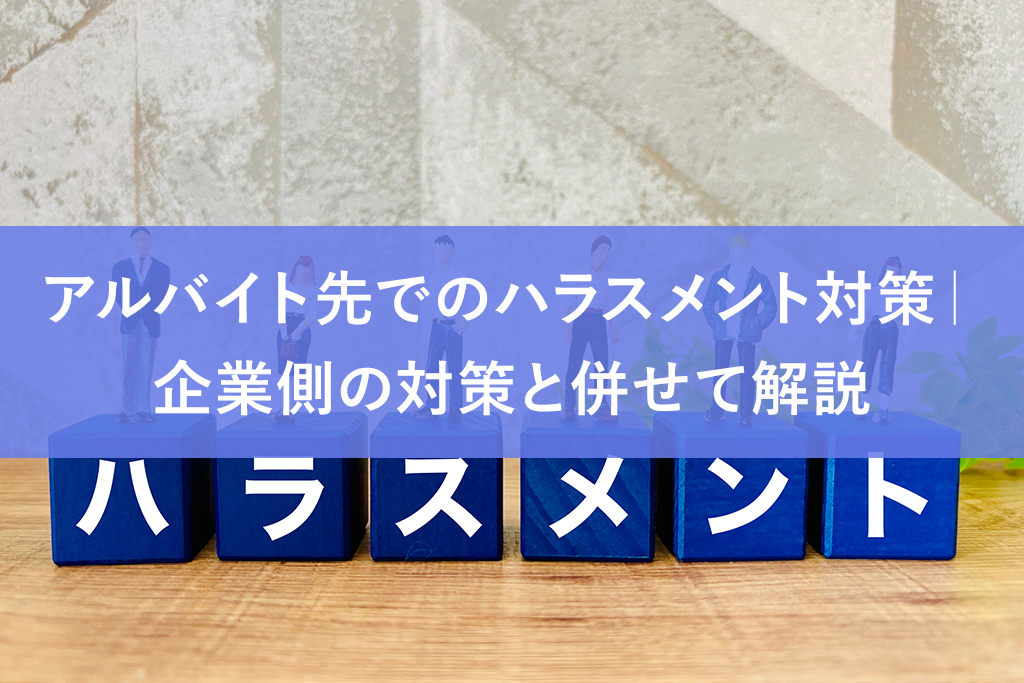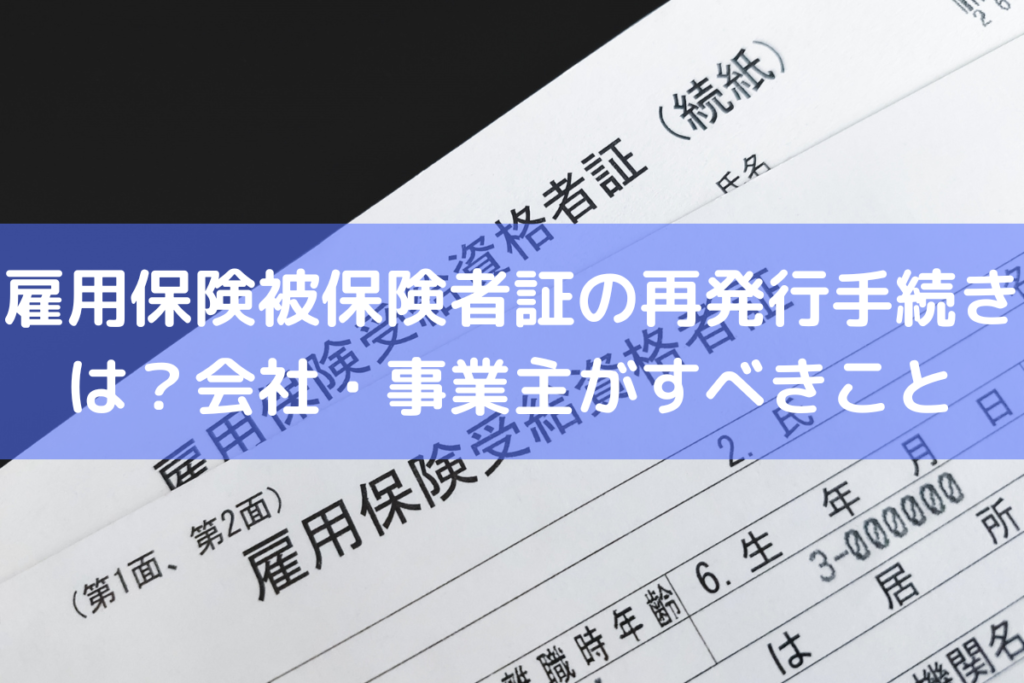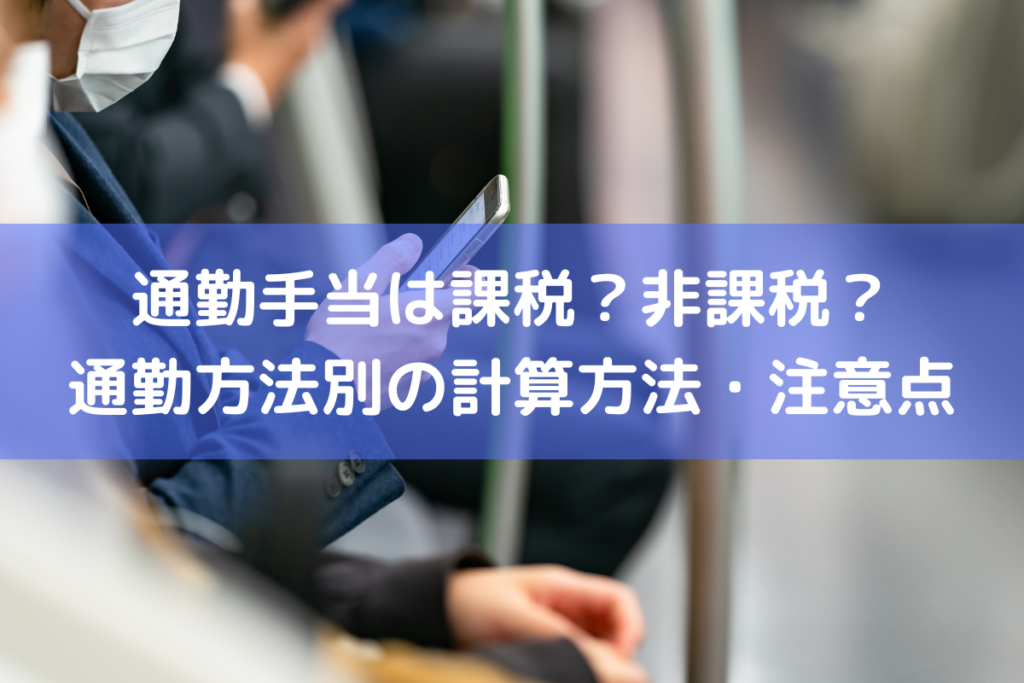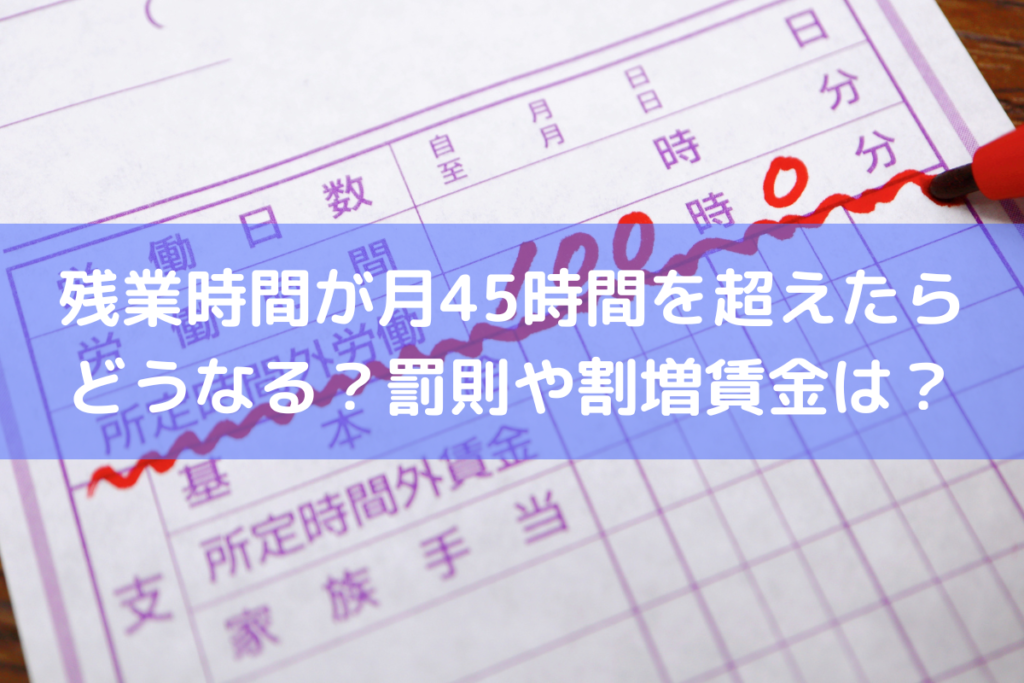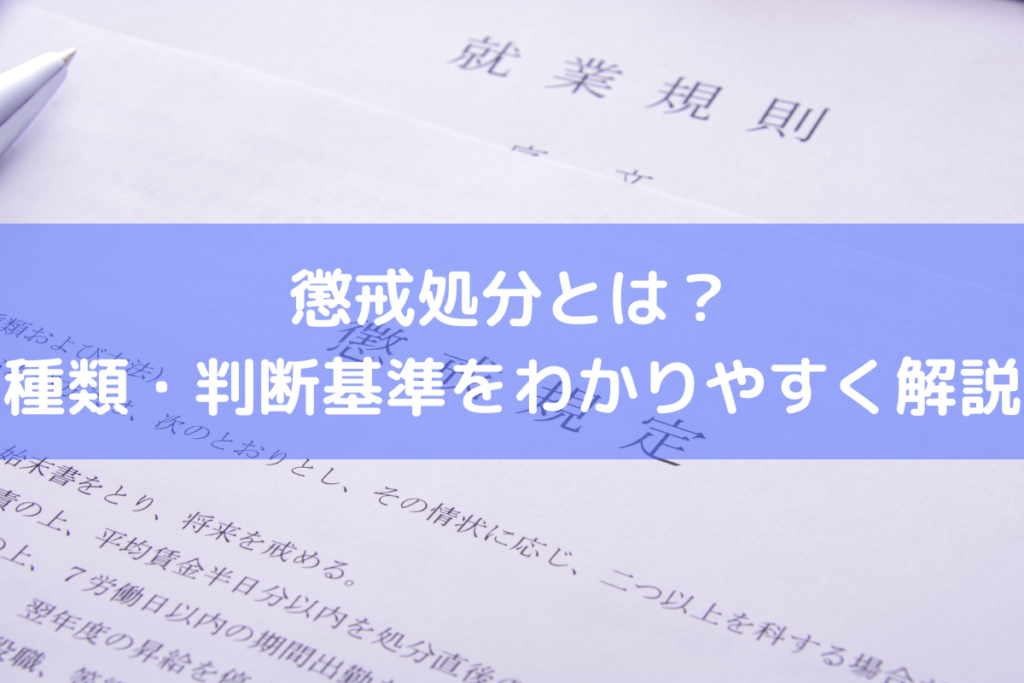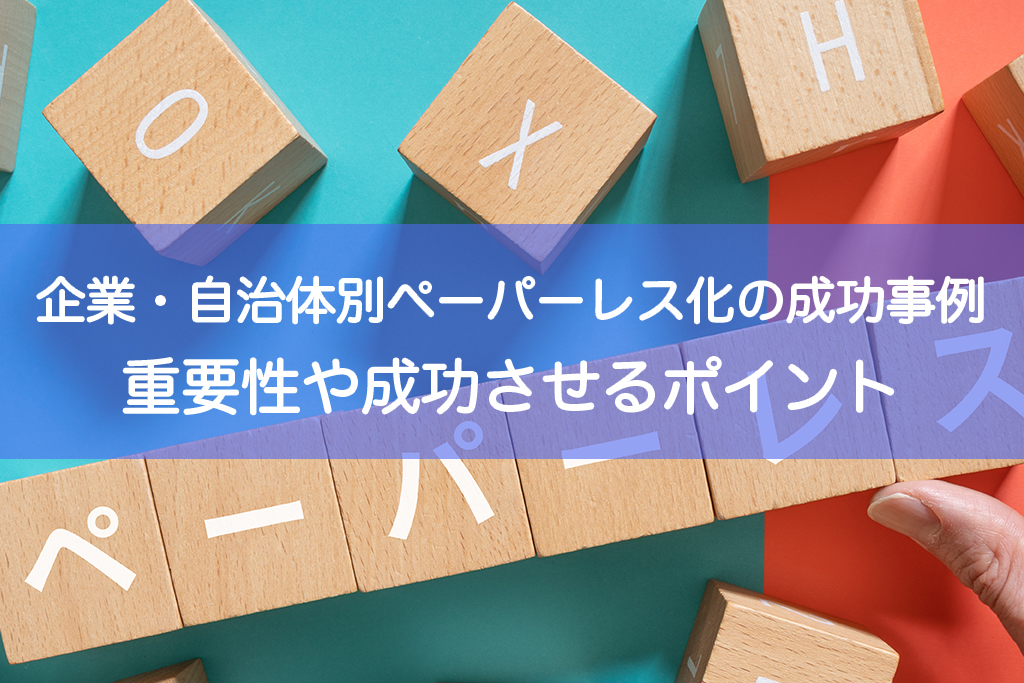カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客等からの、企業や従業員に対する不当な要求や嫌がらせを指します。2025年6月には、ハラスメント対策の強化を含む「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されるなど、今やカスハラは社会的な課題の一つです。
カスハラの被害は、アルバイトにも及びます。企業はアルバイトの定着率を上げるためにも、カスハラ対策を実施し、従業員の安全を守る環境づくりを行なう義務があります。
この記事では、カスハラとクレームの違いや見分け方を解説するともに、アルバイトにも起こりがちなカスハラの実態を説明します。また、ガイドラインの策定など企業が取り組むべきカスハラ対策についても紹介するため、ぜひ最後までお読みください。
カスハラ(カスタマーハラスメント)とは何か?

カスハラとはカスタマーハラスメントを略した用語で、顧客による過度な要求や理不尽なクレームなどにより、企業や従業員に精神的・身体的な苦痛を与える言動のことです。
近年カスハラを問題視する声は多くなっており、2025年6月11日には、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。本法律の概要によれば、カスハラとは以下を指します。
「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること」
引用:厚生労働省「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の概要」
本法律の内容は、カスハラに起因する問題に関する国や事業主、労働者および顧客等の責務を明確化し、事業主に対し雇用管理上必要な措置を義務付けるものとなっています。
また、東京都では2025年4月1日、全国初となる「東京都カスタマーハラスメント防止条例」(通称:東京都カスハラ防止条例)が施行されるなど、カスハラは今や社会で取り組むべき問題です。
なお、カスハラの具体的な内容は「アルバイトが受けるカスハラ事例」にて詳しく解説します。
カスハラとクレームの見分け方
カスハラがハラスメントに該当するのに対し、クレームは企業にとって有益な情報になりえます。そのため企業は、カスハラとクレームの違いを明確に理解しておくことが重要です。ここでは、両者の違いを2つのポイントに絞って紹介します。
1:妥当性の有無
カスハラとクレームの大きな違いは、指摘や要求の妥当性にあります。例えば、企業が提供する商品やサービスの瑕疵や過失を指摘するものは、正当なクレームと判断可能です。
一方で、商品やサービスに瑕疵や過失がないにもかかわらず行なわれる理不尽なクレームや過度な要求、暴力・暴言などはカスハラに該当します。
2:目的が適切であるか
クレームの目的は、商品やサービスの瑕疵や過失の解消です。そのため、「商品を交換してほしい」「サービスを改善してほしい」など建設的な意見が寄せられる場合はクレームだと判断できます。
一方でカスハラの目的は、嫌がらせや過剰な利益の獲得です。例えば、商品やサービスの瑕疵や過失に対して妥当性がない言動や、従業員に対する暴力的、威圧的、継続的、拘束的な言動など社会通念上不適切なものが挙げられます。金銭補償や商品交換の要求なども、妥当性がない場合はカスハラと判断できるでしょう。
アルバイトも標的になるカスハラの実態

アルバイトも、カスハラの標的になる可能性が十分にあります。以下にアルバイトが受けるカスハラの実態を紹介します。
アルバイトが受けるカスハラの実態
2025年1月に公開された、マイナビの「アルバイト従業員へのカスタマーハラスメント実態調査」によると、調査に応じた企業のうち45.7%が、自社のアルバイト従業員が何らかのカスハラを受けたと回答しました。
業種別にみると、販売や接客(パチンコ・カラオケ・ネットカフェ)が77.7%と最も多く、次いで販売や接客(コンビニ・スーパー)が70.3%、ホールキッチン・調理補助(飲食・フード)が55.7%と続きます。
カスハラの被害内容としては、「大きな怒鳴り声を上げられた」や、「理不尽な要望を繰り返し問い合わせられた」「SNSに悪い口コミを書くなど、ブランドイメージを下げるような脅しをされた」などが挙げられています。
参考:アルバイト従業員へのカスタマーハラスメント実態調査 | マイナビキャリアリサーチLab
なぜアルバイトが標的にされやすいのか
アルバイトがカスハラを受けやすい理由は、アルバイトが従事する仕事の多くが接客業であるためです。接客業では顧客と直接のやりとりが発生するほか、クレームの窓口になることもあります。
また、アルバイトには学生など若者が多いため、顧客が「強く言えば要求をのむだろう」と顧客が考え、過度なハラスメントにつながりやすいといえます。
アルバイトが受けるカスハラ事例

アルバイトを含め従業員へのカスハラは、以下の事例が挙げられます。また、過度なカスハラは刑法に抵触する恐れがあるため、併せて紹介します。
妥当性を欠く要求をする
企業の提供する商品やサービスに瑕疵や過失が認められないにもかかわらず、要求を繰り返す行動はカスハラに該当します。また、企業が提供する商品やサービスと関係性がないものについての要求行為も同様です。
暴行や傷害など身体への暴力行為
要求の内容にかかわらず、従業員に暴力を振るう行為は明らかなカスハラです。
従業員を殴る、蹴る、物を投げつけるといった行為を行なった結果、被害者が怪我などを負った場合には、傷害罪(刑法204条)が成立します。また、怪我をしなかった場合でも、暴行罪(刑法208条)が成立します。
暴言や脅迫など精神的な攻撃
従業員に「バカ」「死ね」「殺すぞ」などと暴言を吐いたり、「(従業員の)家族に危害を加える」といった脅迫を行なったりする行為もカスハラです。「早くしろ、クズ」といった乱暴な言葉遣いも含まれます。
従業員に対し、生命・身体・自由・名誉・財産などに害を加える内容を告げたときには、脅迫罪(刑法222条)が成立します。また、人を恐喝して財物を交付させた場合は、恐喝罪(刑法249条)が成立します。
インターネットやSNSへの書き込み
インターネットやSNSに、従業員や企業への不満や悪口などを記入する行為もカスハラの一つです。
不特定多数の人が閲覧できるインターネットやSNS上に、従業員や企業に対する事実に反する書き込みをした場合、名誉毀損罪(刑法230条)が成立します。あるいは、事実に反しない書き込みであっても、内容によっては名誉毀損になります。
従業員を土下座させてその様子をインターネット上に掲載することなども、名誉毀損罪に該当する行為です。
また、公然と人の名誉を毀損した場合には、侮辱罪(刑法231条)が成立します。
不当な要求
不当な要求とは、商品やサービスの瑕疵や過失を追及して従業員に土下座を要求したり、過剰にサービスを求めたりする行為を指します。
脅迫や暴行などの手段を用いて人に義務のないことを行なわせたり、権利の行使を妨害したりした場合は、強要罪(刑法223条)が成立します。
継続的・執拗な言動
短時間の間に繰り返し暴言を吐いたり、複数回にわたりクレームの電話を入れたりする行為もカスハラです。
偽計や威力を用いて人の業務を妨害した場合、業務妨害罪(刑法233条、刑法234条)が成立します。
拘束的な言動
従業員に対し、長時間におよぶ電話をしたり、店舗に居座ったりするカスハラもあります。
店舗などから退去するように求められた際に正当な理由なく従わなかった場合、不退去罪(刑法130条)が成立します。
差別的・性的な言動
顧客が従業員に対する差別的な言動や、性的な言動もカスハラです。例えば、身体への接触、執拗に食事やデートに誘うことなどが該当します。
参考:刑法 | e-Gov法令検索
アルバイトを守るために企業はカスハラを想定したガイドラインを

アルバイトは、顧客と直接コミュニケーションを取る機会が多く、カスハラを受けやすい立場であるといえます。従業員の定着率を上げるためにも、企業はガイドラインを策定し、アルバイトを含む従業員が安心して働ける環境をつくることが重要です。
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、カスハラを想定した事前準備について、以下の取り組みを掲げています。
1.企業が基本方針や基本姿勢を明確に示し、従業員に周知・啓発する
はじめに、企業としてカスハラ対策にどう取り組むのか、基本方針や基本姿勢(ガイドライン)を明確に示すことが大切です。例えば「職場におけるカスハラをなくす」「カスハラから従業員を守る」といった基本姿勢をトップ自らが発信することは、従業員の安心感につながります。
2.従業員のための相談・対応体制を整備する
カスハラの被害に遭った従業員が気兼ねなく相談できるよう、専用の窓口や相談対応者を設置しましょう。
相談対応者としては、現場の状況に精通している上長や、現場の管理監督者が適切です。相談対応者は、相談者へのフォローはもちろん、状況の把握や事実確認、報告、顧客への対応などさまざまな役割を担うことになるため、事前の教育や研修も重要です。
相談窓口に適切な人材を配置することで、迅速な対応が可能となり、問題の早期解決にもつながります。
3.対応方法や手順を策定する
カスハラを受けても慌てずに対応するには、あらかじめ対応方法や手順(マニュアル)を策定しておく必要があります。
ガイドラインやマニュアルの策定にあたっては、自社の業務内容や業務形態、顧客等との関係性も踏まえ、独自の対応方法例を準備しておくことが重要です。トラブルの内容により柔軟な対応が求められるため、さまざまなケースを想定しておくとよいでしょう。
従業員の安全にも配慮し、顧客等への対応は基本的に複数名で行ない、一人で対応させないことも大切なポイントです。
4.対応に関する社内ルールを整備し、従業員等へ教育や研修を行なう
悪質なカスハラに対応できるよう、日頃から従業員に教育や研修を行ないましょう。研修は可能な限り、アルバイトも含めた全従業員が受講できるようにします。
研修内容としては、クレームとカスハラの違いや判断基準など基本的な内容から、パターン別の対応方法、顧客への接し方のポイントや注意点、記録の作成方法などが挙げられます。実際のカスハラ場面を想定したロールプレイングなども取り入れると、より効果的でしょう。
参考:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」
カスハラが実際に起こった際の対応
続いて、実際にカスハラが起きた際の対応方法について、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき解説します。
1.事実関係を正確に確認し、事案に対応する
まずは顧客からのクレームが正当な主張なのか、あるいはカスハラに該当するのかを正確に判断します。
クレームが事実かを判断するためには、顧客や従業員からの確かな証拠や証言に基づいて確認することが重要です。この際、1人で対応するのではなく、管理者などを含めた複数名で判断するとよいでしょう。
実際に商品やサービスの瑕疵や過失があった場合は謝罪し、顧客の要求内容に応じて交換や返金に応じます。商品やサービスの瑕疵や過失がなかった場合には、要求等に応じる必要はありません。
2.従業員への配慮を措置する
カスハラの被害を受けた従業員に対し、すみやかに配慮を行ないます。殴られるなどの暴力行為や、身体に触るなどのセクハラ行為については、まずは従業員の安全を確保します。現場監督者が顧客対応を代わり、状況に応じて警察や弁護士と連携を取りながら進めましょう。
また、被害を受けた従業員がメンタルヘルスに不調をきたしている場合は、産業医や産業カウンセラーなどとも連携し、アフターケアを行なうことが重要です。
3.再発防止への取り組みを行なう
該当のカスハラ問題が解決したあとも、同様の問題が発生しないよう、再発防止の措置を行ないます。具体的には、事案発生時に従業員に対し注意喚起などのメッセージを発信することです。
また、社内事例を検証したうえであらためて防止策を検討するなど、定期的な見直しや改善などの取り組みも重要といえます。
4.その他
相談者のプライバシー保護のために必要と思われる措置を行ないます。カスハラを相談した従業員が不利益を被ることがないことを明確にし、その旨を全従業員に周知しましょう。
参考:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」
まとめ
カスハラとは、職場においてアルバイトを含めた従業員が顧客等から受ける、社会通念上許容される範囲を超えたクレームや不当な要求などの言動のことです。カスハラは従業員の心身の健康を脅かすだけでなく、刑法に抵触する場合もあります。
特にアルバイトは接客業に従事することが多く、カスハラの対象になりやすいといわれています。アルバイトを守るための企業のカスハラ対策としては、あらかじめガイドラインやマニュアルを策定しておくことが重要です。
また、被害に遭ったアルバイトが企業に相談しやすいよう、相談窓口や相談対応者を設置しましょう。被害者がメンタルヘルスに不調をきたしている場合、産業医や産業カウンセラーの協力を得るといったアフターケアも欠かせません。
「バイトルトーク」は、アルバイトと円滑にコミュニケーションを取るためのアプリです。店長とアルバイトが私用SNSを使うことなくコミュニケーションを図れるほか、シフトの提出や調整などシフトマッチング機能も付いています。本部への相談や通報窓口を実装予定のため、ハラスメント対策としても有効です。