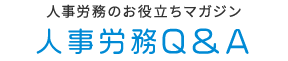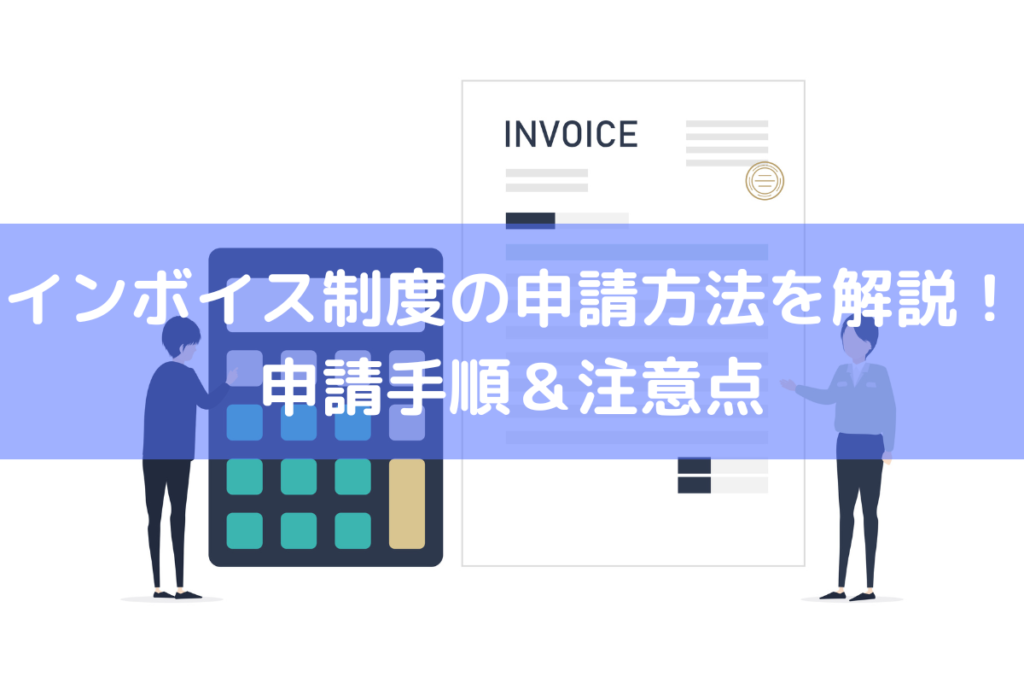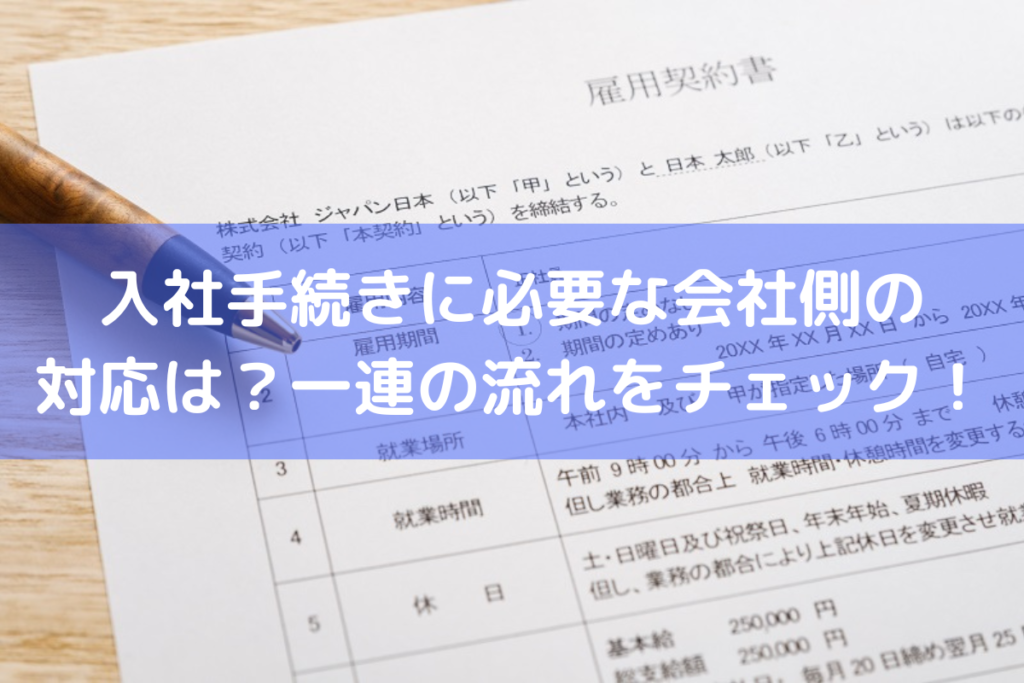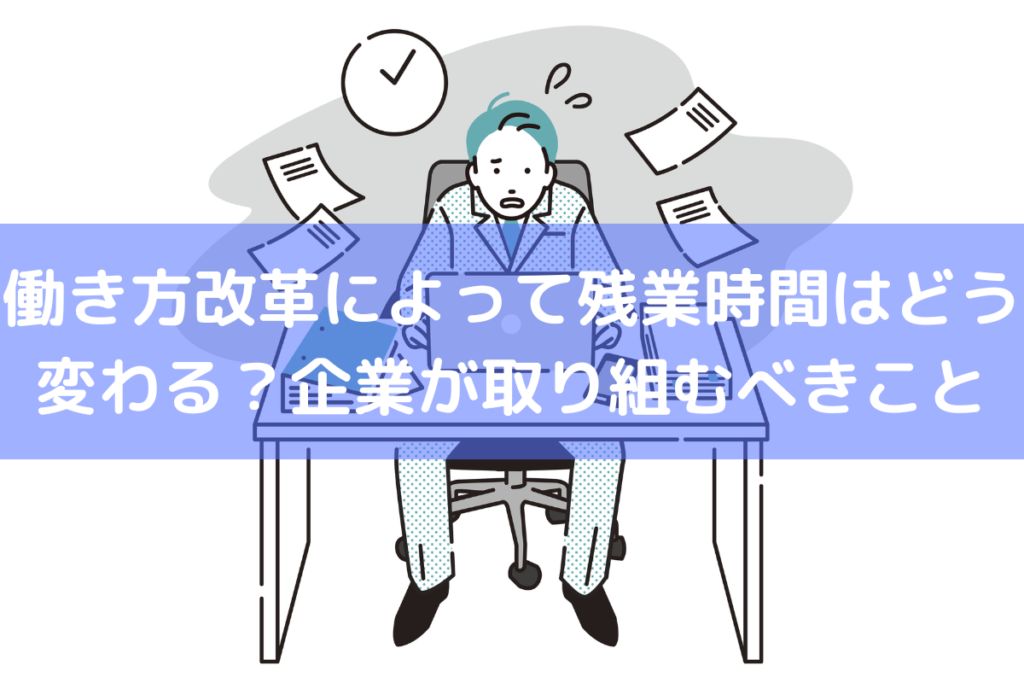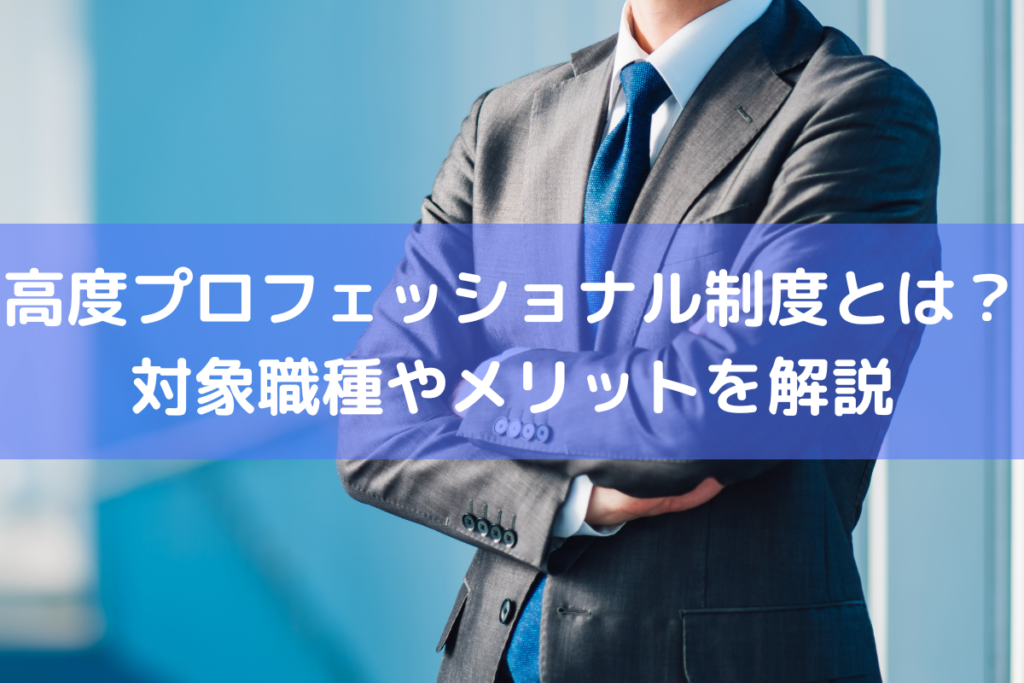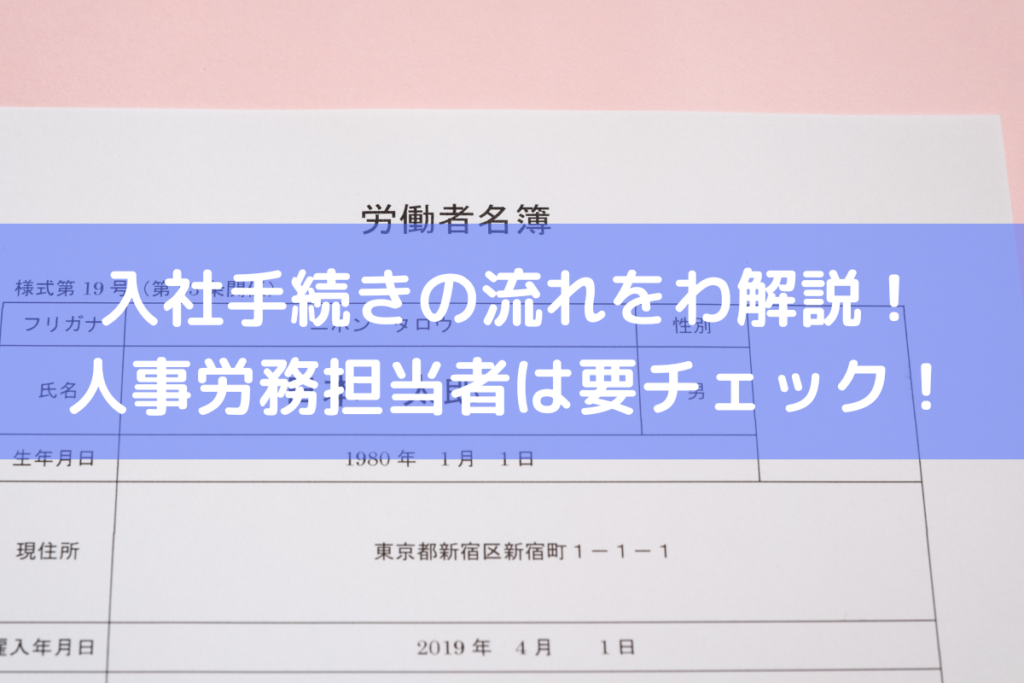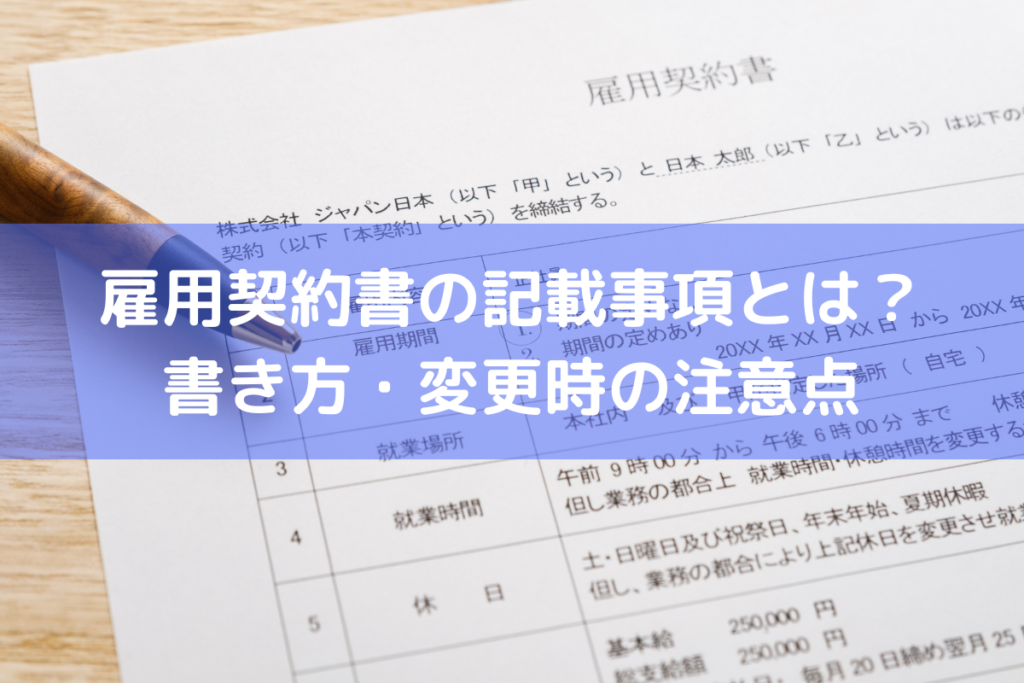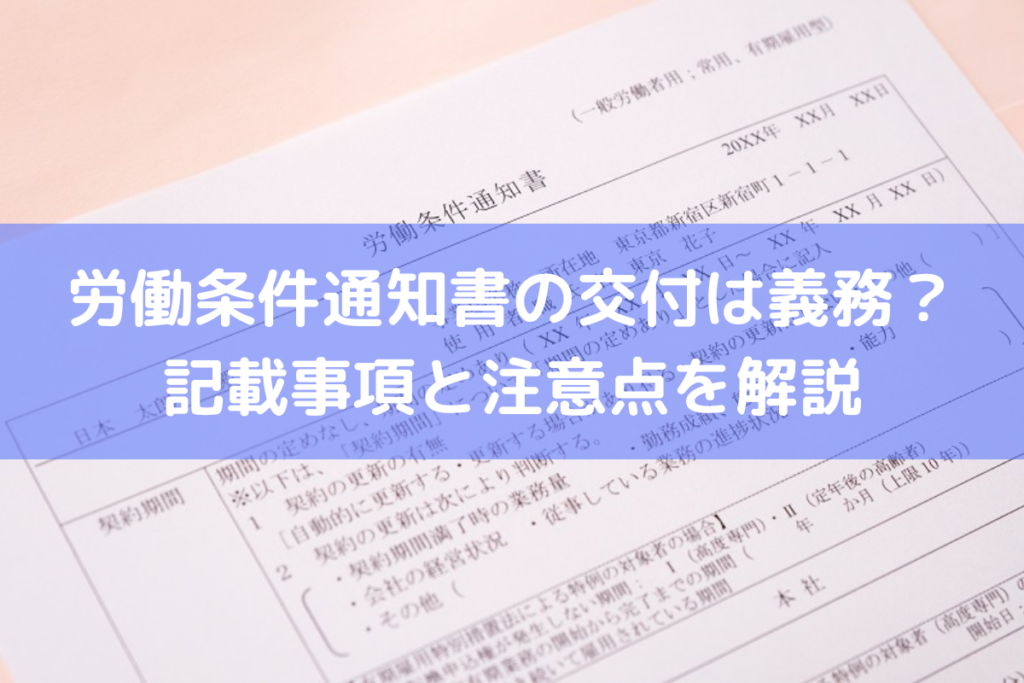
企業の人事や労務担当の方は、労働条件通知書について正しく理解しているでしょうか?
労働条件通知書は雇用契約書と同様に、従業員を雇用する際に必要となる書類です。そして労働条件通知書には、労働基準法にて記載事項が定められています。
法令に基づかない労働条件通知書を交付した場合、従業員とトラブルになり企業の信用度が落ちる可能性もあります。今回は、労働条件通知書を交付する理由やタイミング、作成時の記載事項やよくある質問などについて解説します。
労働条件通知書の交付で失敗しないためにも、改めて労働条件通知書について理解を深めていきましょう。
労働条件通知書とは
労働条件通知書とは、雇用する従業員の労働時間や賃金、勤務地や仕事内容などが記載された書類のことです。後ほど詳しく解説しますが、労働条件通知書には必ず記載しなければならない事項と、必要に応じて記載しなければならない事項に分かれています。
労働条件通知書は、労働基準法に基づき雇用契約を締結する際には交付が必要となる書類です。また、労働条件通知書と混同しやすい書類として雇用契約書があります。労働条件通知書も雇用契約書も役割は似ていますが、細かい点で違いがあります。
では、労働条件通知書と雇用契約書の違いについて、詳しく解説していきましょう。
労働条件通知書と雇用契約書との違い
「雇用契約書」と「労働条件通知書」は役割が同じように感じるかもしれませんが、実は書類の目的がそれぞれ異なります。
労働条件通知書は、事業主が労働者に対し「労働条件を提示」することが目的の書類です。なぜなら、労働基準法第15条により、事業主は労働者に対して労働条件の明示が義務化されているためです。
一方、雇用契約書は、事業主が労働者に対し「労働条件の合意」を目的として作成されます。
雇用契約書は、事業主と労働者が労働条件について合意し「労働契約を締結した証明」となる書類です。そのため、雇用契約書は労働条件通知書とは異なり、双方の合意があって初めて有効となる書類です。
労働条件通知書の場合は、使用者が一方的に交付する書類のため、事業主と労働者の合意を求めるものではありません。また、労働条件通知書は交付が義務化されていますが、雇用契約書の作成は義務化されていません。
なぜ労働条件通知書だけ交付が義務なのか、その理由を解説します。
労働条件通知書の交付は義務?
労働条件通知書の交付は義務化されています。なぜなら、労働基準法第15条第1項により、労働条件の明示が規定されているためです。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
このように、労働基準法第15条第1項にて、労働条件通知書の交付が義務であることが記載されています。そのため、労働条件通知書を交付しない場合は法令違反となります。
労働条件の明示は、労働者が事業主のもとで勤務するかどうかを判断する重要な書類です。労働者とのトラブルを防止するためにも、労働条件通知書は必ず交付しましょう。
労働条件通知書を交付するタイミング
労働条件通知書を交付するタイミングは、次の4つです。
・従業員の入社時
・新卒者の内定時
・労働条件の変更時
・求人募集時
従業員の入社時
従業員が入社する際は、必ず労働条件通知書を交付しなければなりません。従業員とのトラブル防止のためにも、労働条件通知書の交付と併せて雇用契約書についても作成しておきましょう。
また、労働条件通知書と雇用契約書の内容を兼用し、1枚の書類にまとめて交付することも可能です。
新卒者の内定時
新卒者を雇用する際は、内定時までに労働条件通知書を交付しましょう。新卒者に内定を出す際には、労働申込みを承諾する旨を記載した「内定通知書」を出します。
内定通知書を出す際に労働条件通知書も併せて交付し、具体的な労働条件について内定者に確認してもらいましょう。新卒者については入社日当日ではなく、内定時に労働条件通知書を交付し、労働条件についてきちんと明示しておくことが必要です。
労働条件の変更時
労働条件を変更する際は、労働者に対して変更となる労働条件の通知と合意が必要です。労働条件を変更する際は、原則として対象となる労働者の合意が必要です。労働者の合意なく労働条件を変更することは、下記の労働契約法8条に違反する行為となります。
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
引用元:厚生労働省|労働契約法(◆平成19年12月05日法律第128号)
従業員とのトラブル防止のためにも、労働条件を変更する際は「労働条件変更通知書」を作成し、労働条件の変更を客観的に証明できるようにしておきましょう。
求人募集時
ハローワークや求人サイトなどで求人を募集する際も、労働条件を明示しなければなりません。とはいえ、求人媒体によってはスペースの関係ですべての労働条件を掲載するのが難しい場合があります。
その際には、賃金や休日日数、業務内容や勤務場所などの基本的な情報を明示しておき、求職者から応募があった際に、労働条件の詳細を明示するようにしましょう。
労働条件通知書に明示する事項

労働条件通知書に明示する事項は、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の2つに分かれており、いずれも労働基準法施行規則第5条第1項により規定されています。
絶対的明示事項は必ず記載する項目で、相対的明示事項は必要に応じて記載しなければならない項目です。絶対的明示事項と相対的明示事項に記載する項目は、それぞれ次のとおりです。
| 絶対的明示事項 | 相対的明示事項 |
| ・契約期間に関すること ・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関すること ・就業の場所、従事する業務に関すること ・始業や終業時刻、休憩や休日に関すること ・賃金の決定方法や支払い時期などに関すること ・退職に関すること(解雇事由も含める) ・昇給に関すること | ・退職手当に関すること ・賞与などに関すること ・食費や作業用品などの負担に関すること ・安全衛生に関すること ・職業訓練に関すること ・災害補償などに関すること ・表彰や制裁に関すること ・休職に関すること |
労働条件通知書を作成する際の注意点
では、実際に労働条件通知書を作成する際はどのような点に注意しなければならないのでしょうか?主な注意点は6つあります。それぞれについて詳しく解説していきましょう。
・絶対的明示事項は必ず記載する
・短時間・有期雇用労働者は追記が必要
・相対的明示事項は必要に応じて記載する
・住所や氏名の欄は空白にしておく
・書式はテンプレートを活用する
・雇用契約書と併用して明示する
絶対的明示事項は必ず記載する
繰り返しにはなりますが、労働条件通知書に記載する絶対的明示事項は、労働基準法により必ず記載しなければならない項目です。絶対的明示事項のそれぞれの項目について、一つずつ確認していきましょう。
契約期間に関すること
契約期間の定めがあるかどうかを記載します。契約期間がある場合は具体的な年月日を記載しましょう。
就業場所や従事する業務
実際に勤務先となる店舗名や会社名を記載します。業務内容については人事や労務、経理など具体的な業務内容を記載し、異動や転勤の可能性がある場合は、その旨も記載します。
始業や終業時刻
業務の開始時間と終了時間を記載します。フレックスタイム制など業務時間が固定されない場合は、その旨も記載するか、別途資料を添付しましょう。
休憩や休日
休憩時間の具体的な時間数を記載します。休日については法定休日の他、年次有給休暇や特別休暇制度など、具体的な休日制度の有無について記載します。
賃金の決定方法や支払時期
基本賃金や各種手当、時間外労働の計算方法など、具体的な賃金の算出方法を記載します。支払時期については、締め日と支払日、支払い方法を記載しましょう。
退職に関すること
定年制度や再雇用制度などについて記載します。また、退職の際の手続きや解雇事由についても、併せて記載しておきましょう。
また、上記の項目に加えて、パートタイマーやアルバイトなどの短期雇用者については、別途記載する項目があります。記載項目については、次項で解説します。
短時間・有期雇用労働者は追記が必要
パートタイマーやアルバイトといった短期雇用者については、下記の項目も明示しなければなりません。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 雇用管理についての相談窓口や担当者名など
絶対的記載事項では雇用区分により追記項目があることを、理解しておきましょう。絶対的明示事項の作成に迷った際には、厚生労働省のホームページ(労働基準法の基礎知識)を参考にするとスムーズです。
相対的明示事項は必要に応じて記載する
労働条件通知書の相対的明示事項については、必要に応じて記載が求められます。
- 退職手当に関すること
- 賞与などに関すること
- 食費や作業用品などの負担に関すること
- 安全衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償などに関すること
- 表彰や制裁に関すること
- 休職に関すること
上記のような項目は企業によって規定の有無が異なるため、規定があるならば絶対的明示事項と併せて記載しておきましょう。
ちなみに、相対的明示事項は絶対的明示事項とは違い、書面での交付が義務化されているわけではありません。絶対的明示事項については、書面での交付が必要です。
とはいえ、口頭での明示は客観的証拠が残らないため、トラブル防止の観点からも書面で交付することをおすすめします。
住所や氏名の欄は空白にしておく
労働条件通知書と雇用契約書を兼用して交付する場合は、労働者の住所や氏名の欄は空白にしておきましょう。企業側で事前に労働者の住所や氏名を記載していた場合、労働者から「勝手に署名や捺印がされていた」と主張されることで、トラブルになる可能性があります。
労働条件通知書と雇用契約書を兼任して交付する際は、労働者が直筆で署名できるよう住所や氏名の欄は空白にしておくことが鉄則です。
書式はテンプレートを活用する
労働条件通知書を作成する際は、間違いを防ぐためにもテンプレートを活用しましょう。厚生労働省のホームページでは、労働条件通知書のテンプレートがダウンロードできます。
また、厚生労働省のホームページでは上記の労働条件通知書だけではなく、労働基準法関係のテンプレートを多数公開しています。
上記のテンプレートを自社の内容に合わせてカスタマイズすることで、不備のない書類を作れるでしょう。
雇用契約書と併用して明示する
雇用契約書の作成は義務ではありませんが、できれば労働条件通知書と併せて明示することを強く推奨します。
労働条件通知書とは異なり、雇用契約書は事業主と労働者の間で労働契約に合意を得られている事実を、客観的に証明できる書類です。万が一、従業員から訴訟などを起こされた際には、雇用契約書の有無で企業の優位性が大きく異なります。
従業員とのトラブルを防止し、万が一の際には客観的な証拠として提示できるよう、雇用契約書も労働条件通知書と同様に作成しておきましょう。
労働条件通知書に関してよくあるQ&A
労働条件通知書に関するよくあるQ&Aをまとめました。労働条件通知書についての理解を深めるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
労働条件通知書を交付しないとどうなりますか?
労働条件通知書の交付を怠った場合、労働基準法にもとづき、次のような罰則が事業主に科せられる可能性があります。
- 労働基準法第13章第117条:1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金
- 労働基準法第13章第118条:1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
- 労働基準法第13章第119条:6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
- 労働基準法第13章第120条:30万円以下の罰金
労働条件通知書の交付は事業主の義務です。労働基準法にもとづき、必ず労働者へ交付しましょう。
労働条件通知書の明示は全従業員が対象ですか?
労働条件通知書の明示は、正社員やアルバイトといった雇用区分に関係なく、雇用者全員に対して必要です。新たに従業員を雇用する際はもちろん、有期雇用労働者が契約を更新する際にも、改めて労働条件通知書の明示が必要となります。
労働条件通知書をメールで送付することは可能ですか?
労働条件通知書はメールでの交付も可能です。ただし、メールで交付する際は下記の項目に留意しなければなりません。
- 労働者が希望した場合に限り、交付できること
- 交付方法は、FAX・メール(ショートメールは不適切)・SNSのいずれかであること
- 添付ファイルで送付し、印刷や保存ができるようにすること
- データ送付後、労働者にデータ到着の有無を確認すること
- 送付データを出力して保存するように、労働者に伝えること
上記の労働条件通知書の電子交付については、厚生労働省のホームページ(「労働基準法施⾏規則」 改正のお知らせ|厚生労働省)でも確認できます。なお、労働者が希望していないにもかかわらず、メール等のみで労働条件通知書を交付することは、労働基準関係法令の違反となるため注意しましょう。
まとめ
労働条件通知書について、労働条件通知書を交付する理由や労働者に交付するタイミング、記載項目や作成時の注意点などについて解説しました。
労働条件通知書は、事業主が労働者を雇用する際に明示が義務化されている書類です。明示を怠ると、労働基準関係法令の違反となり処罰される可能性があります。
労働条件通知書には絶対的明示事項と相対的明示事項の2つの記載項目があり、労働基準法にもとづき規定された項目を正しく記載しなければなりません。
また、労働条件通知書と雇用契約書とでは、労働条件通知書が労働者に対し「労働条件を提示」することに対し、雇用契約書は「合意」を求めるという違いがあります。
企業の人事や労務担当者は労働条件通知書や雇用契約書などの違いを正しく理解し、従業員とのトラブルを招かないように気をつけましょう。
当社ディップ株式会社では、従業員の入社手続きをサポートする「人事労務コボット」を提供しています。

人事労務コボットは入社手続き等のペーパーレス化を実現することで、業務にかかる時間を約85%削減することが可能です。面倒な入社手続きの効率化につながるおすすめのDXツールです。 入社手続きを効率化させるためにも、ぜひ導入をご検討ください。