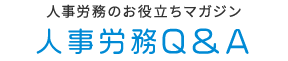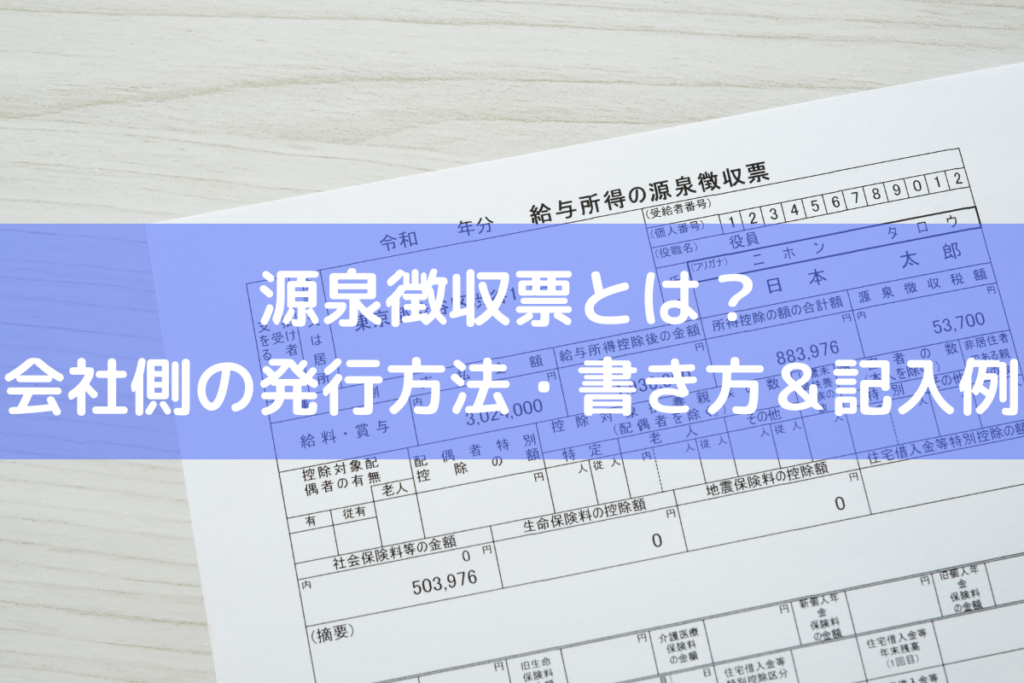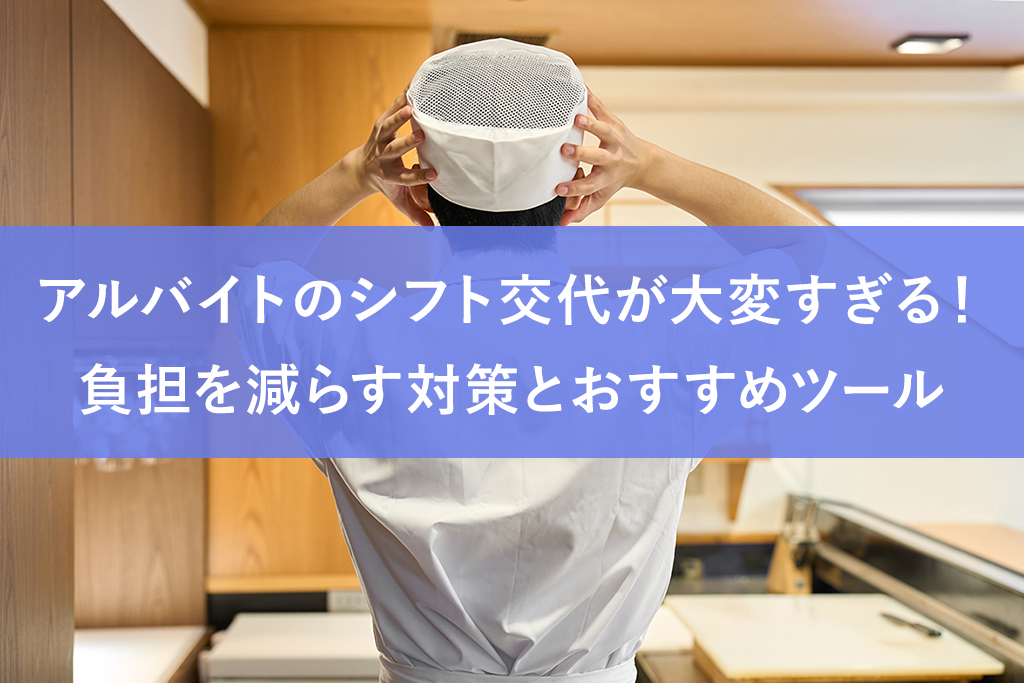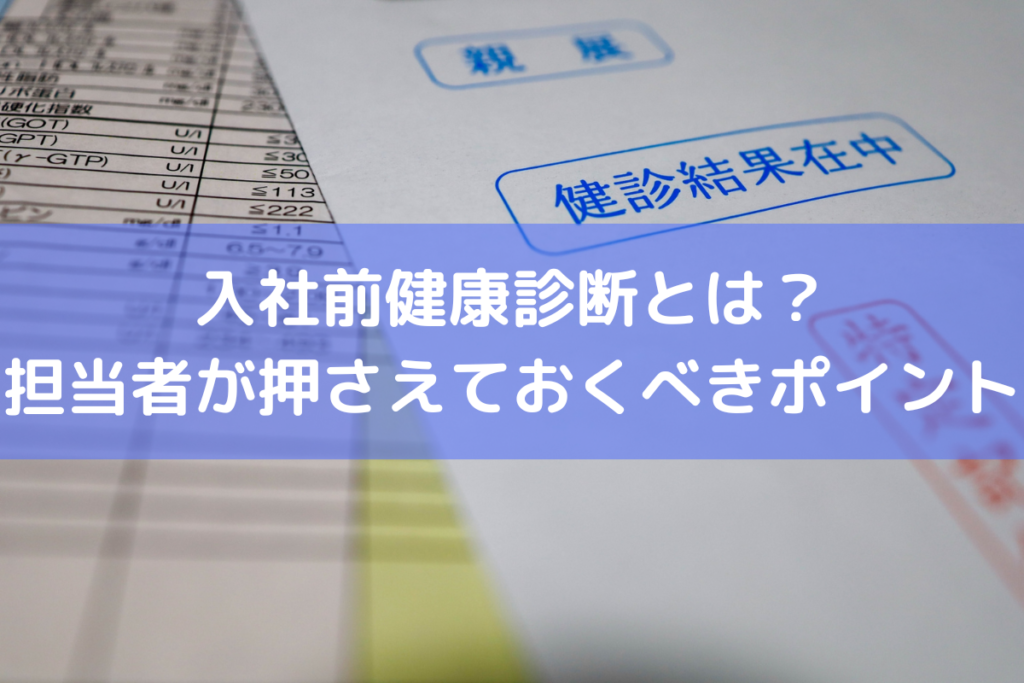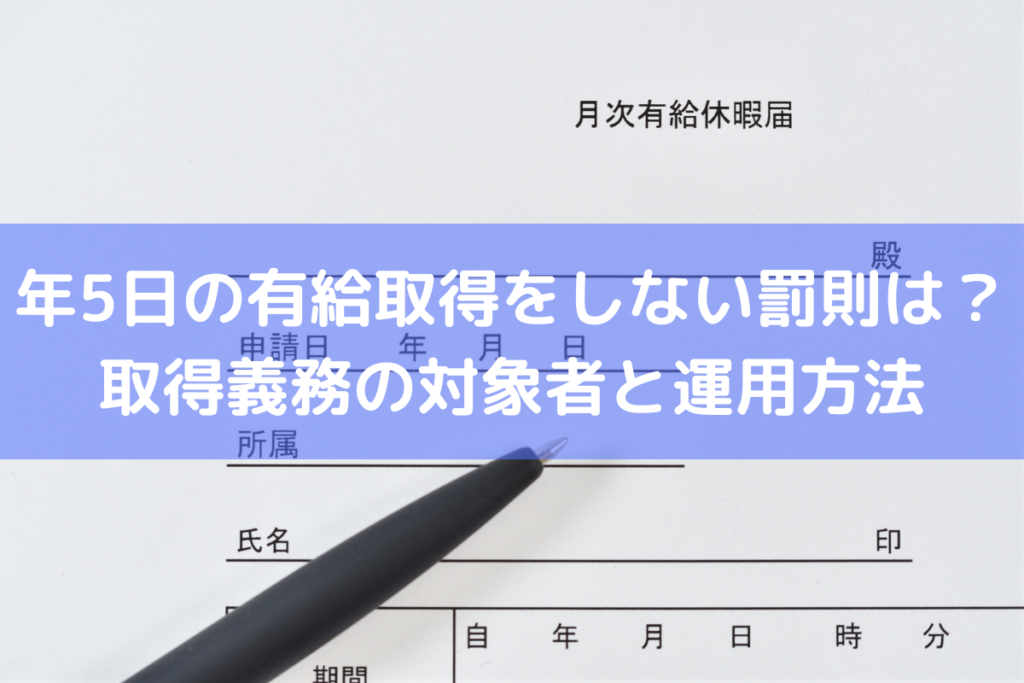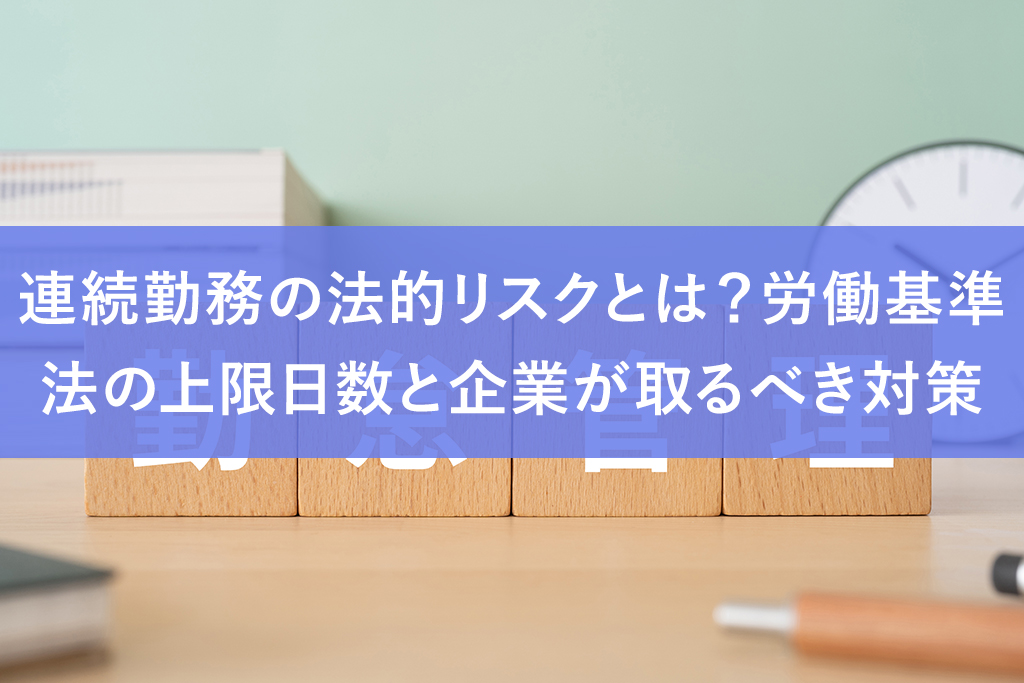
慢性的な人手不足などの理由から、従業員に連続勤務をさせてしまう状況に置かれている企業も存在するでしょう。
今後もそのような状況が続くようであれば、従業員の健康に悪影響をおよぼすことや、法律に違反してしまう危険性があることを理解しておかなければなりません。
この記事では、連続勤務に関する労働基準法上の制限や例外、企業に求められる対策について詳しく解説します。この記事が、安心・安全な職場環境づくりを目指す担当者の方の一助になれば幸いです。
労働基準法における連続勤務の上限

連続勤務については、労働基準法で一定の上限が定められています。具体的に、どのように定められているかを確認しておきましょう。
原則として週1回の休日付与義務
労働基準法第35条では、「使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定されています。これは、心身の健康を守るための最低限の基準のため、順守しなければなりません。
ただし、休日の曜日が固定されていない場合、休日の取り方によっては最大で12日間連続勤務することが理論上は可能です。例えば、前週の日曜日と翌週の土曜日に休みを設定すれば、その間は連続勤務日となり、12連勤が成立します。
しかし、12連勤は現実的には望ましくありません。過労による健康被害や生産性の低下を招くうえ、労働基準法第36条(36協定)の時間外労働の上限規制にも抵触する可能性があるため、避けるべき勤務形態といえるでしょう。
変形労働時間制における例外
変形労働時間制とは、業務の繁閑に応じて、一定期間内の労働時間を柔軟に調整できる制度のことです。この制度では、定められた期間の平均労働時間が週40時間以内であれば、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた勤務が認められます。
なお、変形労働時間制を採用した場合は原則6日間、1年単位の変形労働時間制に限っては、業務の都合により12日間が連続勤務の上限になります。
ただし、制度を導入するには労使協定を締結し、就業規則に記載しなければなりません。また、連続勤務が可能とはいえ、長期的な健康被害を防ぐためにも適切な労務管理が求められます。
36協定による時間外労働の上限
36協定とは、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」と呼ばれる、労働基準法第36条に基づく労使間の協定のことです。この協定がなければ、企業は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働を命じることはできません。
また、法定休日に労働をさせる場合も、この36協定の締結が必須です。法定休日とは労働者に必ず与えなければならない休日のことで、連続勤務日に法定休日を含む場合には、36協定を適切に締結し、届け出なければなりません。
時間外労働の上限についても定めがあり、原則として「月45時間、年360時間」とされています。これを超える場合には、さらに細かい条件を記載したうえで締結する必要があり、違反すれば企業に対する行政指導や罰則の対象となります。
連続勤務の例外規定とその適用

連続勤務には原則的な上限がある一方で、一定の職種や制度においては例外的な扱いが認められています。これらの例外規定を正しく理解し、適切に適用することで、法的トラブルの回避につながるでしょう。
管理監督者への適用除外
管理監督者とは、企業内において経営者と一体的な立場で業務を遂行する者のことです。管理監督者に該当するかどうかは、役職に就いていることよりも、人事権や労働時間の裁量などを実質的に有しているかなどが判断基準となります。
労働基準法第41条第2号では、この管理監督者に対して労働時間、休憩、休日の規定を適用しないと定めています。そのため、連続勤務に関しても法的な上限は適用されません。
しかし、管理監督者であっても人間である以上、過度な勤務は健康を害するリスクがあります。長時間労働による過労死の問題が社会的に注目されている今、企業としては管理監督者に対しても適切な労務管理と健康配慮を行なう責任があるといえるでしょう。
特定業種における特例
かつては、建設業、医師、運送業、鹿児島県や沖縄県の砂糖製造業といった特定業種に限り、36協定による時間外労働の上限規制が猶予、除外されていました。
しかし、2024年4月1日より、これらの業種および職種に対しても一般的な上限規制が適用されています。ただし、研究開発職と一部を除いた公務員については、2024年4月1日以降も36協定の適用外です。
また、以下の対象者についても36協定の上限が適用除外となっています。
・18歳未満の労働者
・育児・介護に関する申し出を行なった従業員
・妊産婦から請求のあった従業員
・管理監督者
未成年や妊婦など特別な保護が必要な従業員については、企業も法規制の変化に対応した労務管理が求められるでしょう。
変形休日制の導入とその影響
変形休日制とは、週1日の休日付与が難しい場合に、4週間のなかで4日以上の休日付与を例外的に認める制度のことです。この制度では、4週間の最初と最後に休日を設定すれば、最大で24日間の連続勤務が可能となります。
【例】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1週目 | 休日 | 休日 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 |
| 2週目 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 |
| 3週目 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 |
| 4週目 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 休日 | 休日 |
この制度を導入するには、就業規則への明記が必要であり、労働者への説明も求められます。
しかし、24連勤ともなると、労働者の健康や集中力の低下は避けられず、労災や生産性低下のリスクも増大するでしょう。そのため、制度としての合法性はあっても、現実的な運用には十分な配慮が必要です。
連続勤務が引き起こす企業の法的リスク
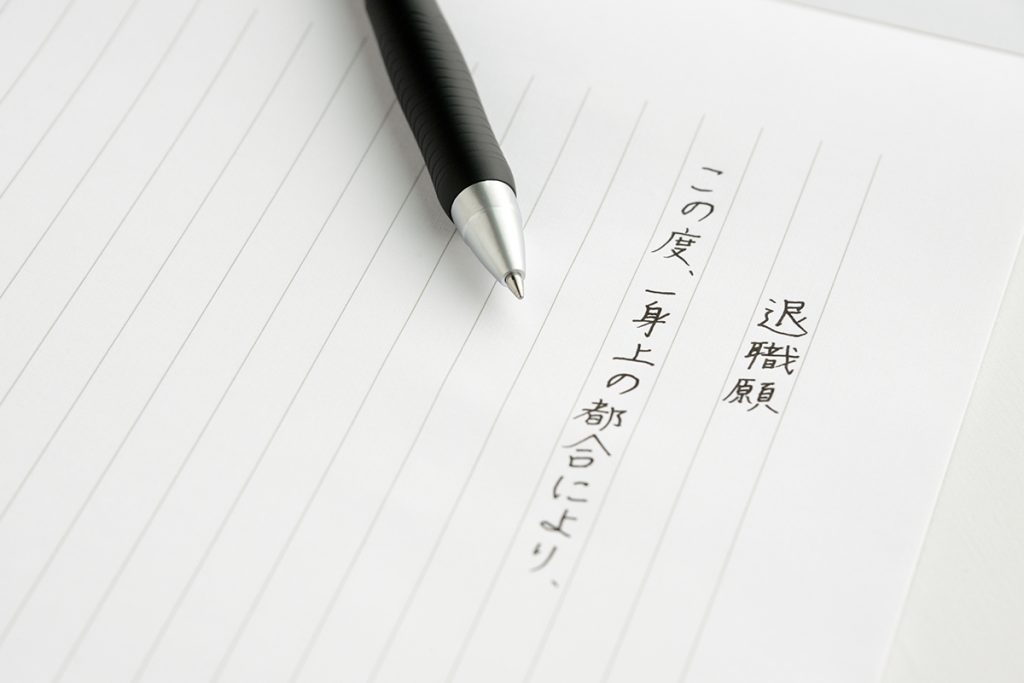
連続勤務が法律の定める上限を超えた場合、企業はさまざまな法的リスクにさらされることになります。
労働基準監督署による是正勧告や罰則
労働基準監督署は、企業の労働環境に違反があると判断した場合、「是正勧告」を行ないます。これは、違反事項の改善を促す行政指導であり、法定休日の付与義務に違反するケースも対象です。
労働基準法第35条に違反した場合、企業には6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、是正勧告を受けた段階で企業名が公表される場合もあり、企業の信頼性が大きく揺らぐおそれもあるでしょう。
従業員の健康被害と安全配慮義務違反
企業は労働契約に基づき、労働者の生命や健康を守る「安全配慮義務」を負っています。無理な連続勤務を強いれば、心身の不調やうつ病などの健康被害が発生し、最悪の場合には過労死に至る可能性もあるでしょう。
こうした状況が発生した場合、企業は損害賠償責任を問われる可能性が高く、訴訟リスクもともないます。また、安全配慮義務違反が認められれば、社会的な信頼も大きく損なわれるため注意が必要です。
離職率の増加と企業イメージの低下
連続勤務や長時間労働が常態化すると、従業員の疲労やストレスが蓄積し、モチベーションの低下を招きます。その結果、退職を選択する社員が増え、離職率が高まる可能性も否定できません。
離職率が上昇すれば、新たな人材を採用・育成するためのコストがかさみ、組織の生産性も低下します。さらに、ブラック企業のレッテルを貼られることで、採用活動や取引先との関係にも悪影響を与えかねません。
企業が継続的に成長していくためには、働きやすい職場環境づくりと法令遵守の両立が重要です。
従業員への影響と健康リスク
連続勤務が常態化すると、従業員の心身に深刻な健康被害がおよぶ可能性があります。ここでは、過労による健康障害や労働災害、ワークライフバランスへの悪影響について詳しく解説します。
過労による心身の健康被害
長時間労働を続けることで、身体的疲労が慢性化し、心臓病や脳出血など命にかかわる病気を引き起こすリスクが高まります。
また、十分な休息が取れないことで精神的ストレスも蓄積し、うつ病などの精神疾患を発症するおそれもあるでしょう。
心身が常に緊張状態にさらされることで、健康だけでなく仕事のパフォーマンスにも悪影響をおよぼします。
さらに、疲労がたまった状態では集中力や判断力が低下し、業務効率が著しく落ちるため、生産性の面でもマイナスです。連続勤務がもたらす健康被害は、企業にとっても深刻な課題といえるでしょう。
労働災害や労災認定の可能性
長時間勤務や連続勤務は、疲労の蓄積や集中力の低下によって労働災害のリスクを高めます。物理的な事故にとどまらず、精神疾患を発症することもあり得るでしょう。
労災として認定されるかどうかは、「業務遂行性」と「業務起因性」によって決まります。特に、精神疾患については、職場でのストレス要因や勤務状況が重要視されます。
企業が過重労働を放置すると、労災認定を受けるリスクが高まり、法的責任も問われかねません。
ワークライフバランスの崩壊
肉体的な疲労は比較的短期間で回復可能ですが、精神的なストレスやうつ状態は長期にわたるケアが必要です。
こうした状況が続くと、従業員のワークライフバランスは崩れ、仕事に対する意欲や満足度が低下していきます。やがて職場へのエンゲージメントが損なわれ、離職や人材流出にもつながってしまうでしょう。
企業にとって、従業員の働きやすい環境づくりは持続的成長に不可欠であり、ワークライフバランスの維持は極めて重要な要素といえます。
連続勤務における企業が取るべき対策

企業が従業員の健康を守り、法的リスクを回避するためには、連続勤務を防ぐ体制づくりが重要です。ここでは、そのための具体策を解説します。
勤怠管理システムの導入と活用
過重労働を未然に防ぐには、勤怠管理システムの導入が有効です。従業員の勤務状況を即時に把握できるため、勤務時間の見える化によって透明性の高い職場環境を実現できるでしょう。
また、勤怠データを収集・分析することで、業務量や作業フローの最適化にもつながります。手作業による集計では見落としがちだった過剰労働や休日労働も、システムによって効率的に管理できるため、コンプライアンス強化や生産性向上を図ることが可能です。
シフト管理の見直しと適正な人員配置
シフト管理の見直しは、特定の従業員に業務が集中するのを防ぐうえで非常に重要です。全体の業務内容や繁閑のバランスを把握し、適切な人員配置を行なうことで、従業員一人ひとりの負担を軽減できます。
また、業務が属人化しないように、役割や責任を明確にし、チームで協力し合える体制を構築することも大切です。繁忙期には一時的な人員増強や、業務分担・外部委託なども選択肢となるでしょう。
状況に合わせたシフト調整により、従業員の健康と組織の生産性を守ることができます。
勤務間インターバル制度の導入
勤務間インターバル制度とは、終業から翌日の始業までに一定時間以上の休息時間を確保する制度のことです。これにより、従業員は十分な睡眠や生活時間を確保でき、心身のリフレッシュが可能となります。
明確な時間は定められていませんが、9~11時間のインターバルが望ましいとされています。この制度を導入することで、過労の防止やワークライフバランスの改善が期待でき、企業イメージの向上にもつながるでしょう。
就業規則の整備と従業員への周知
企業は、従業員とのトラブル回避や安全面への配慮のためにも、就業規則を整備する必要があります。労働時間や休憩時間、シフト管理のルールが明文化されれば、従業員の安心感にもつながるでしょう。
就業規則を作成したあとは、労働者全員に対して周知することが法律で義務付けられています。掲示、配布、社内ポータルでの共有など、労働者がいつでも確認できる手段を講じることが重要です。
連続勤務の上限を超えないようにシフト調整する方法
人手不足が深刻化するなか、連続勤務を防止し、企業の労務リスクや従業員の負担を減らすためには、効率的なシフト調整が不可欠です。
その対策として「バイトルトーク」のような連絡用アプリの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
バイトルトークでは、店長とアルバイトの間でのコミュニケーションを円滑にし、シフト希望の確認や調整が簡単に行なえます。急な欠勤や変更があった場合でも、シフトマッチング機能によってスムーズにシフト交代ができるでしょう。
まとめ
連続勤務は、従業員の健康を損なうだけでなく、企業にとっても法的リスクとなり得ます。過労による健康被害や労働災害、ワークライフバランスの崩壊を防ぐには、シフト調整や勤怠管理を徹底することが大切です。
「バイトルトーク」のようなシステムを活用し、従業員が安心して働ける職場環境を整えることが、企業の持続的な成長につながるでしょう。