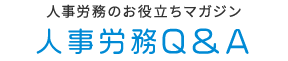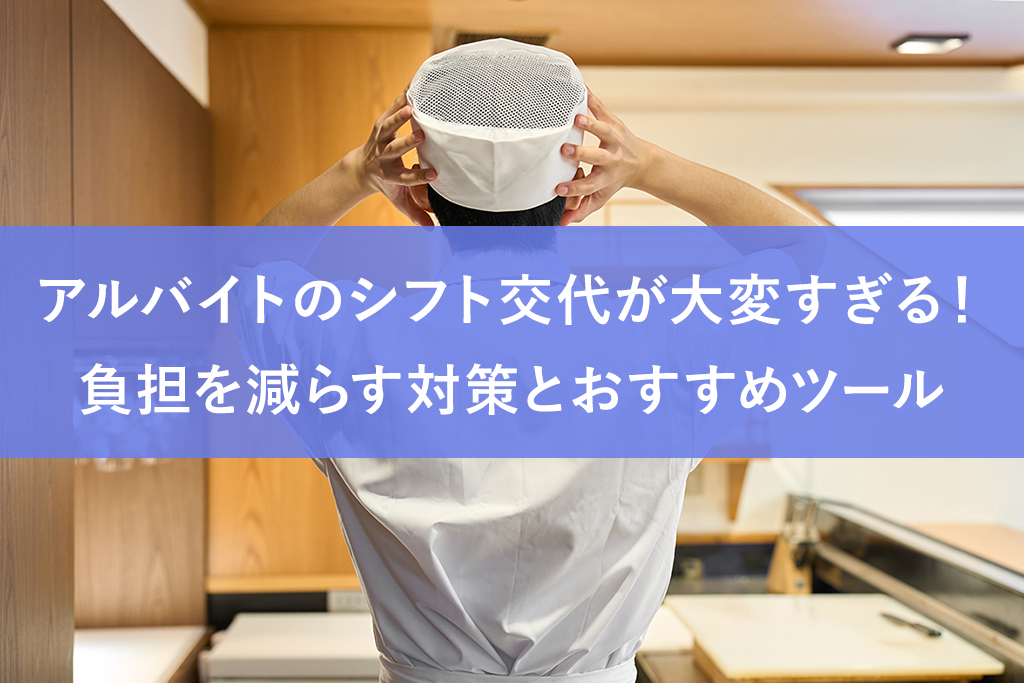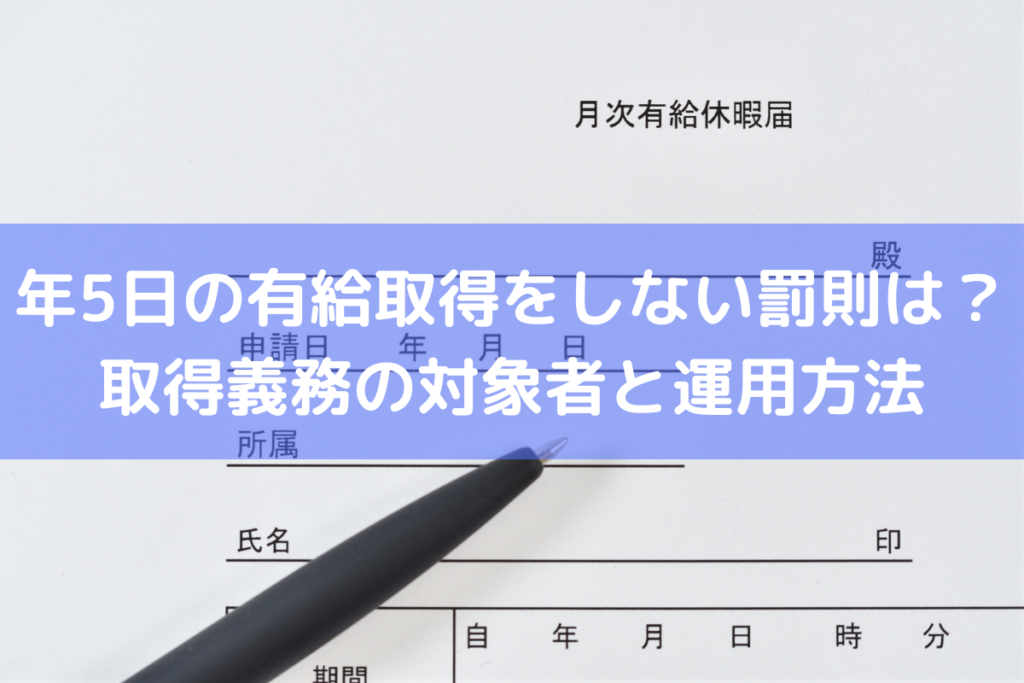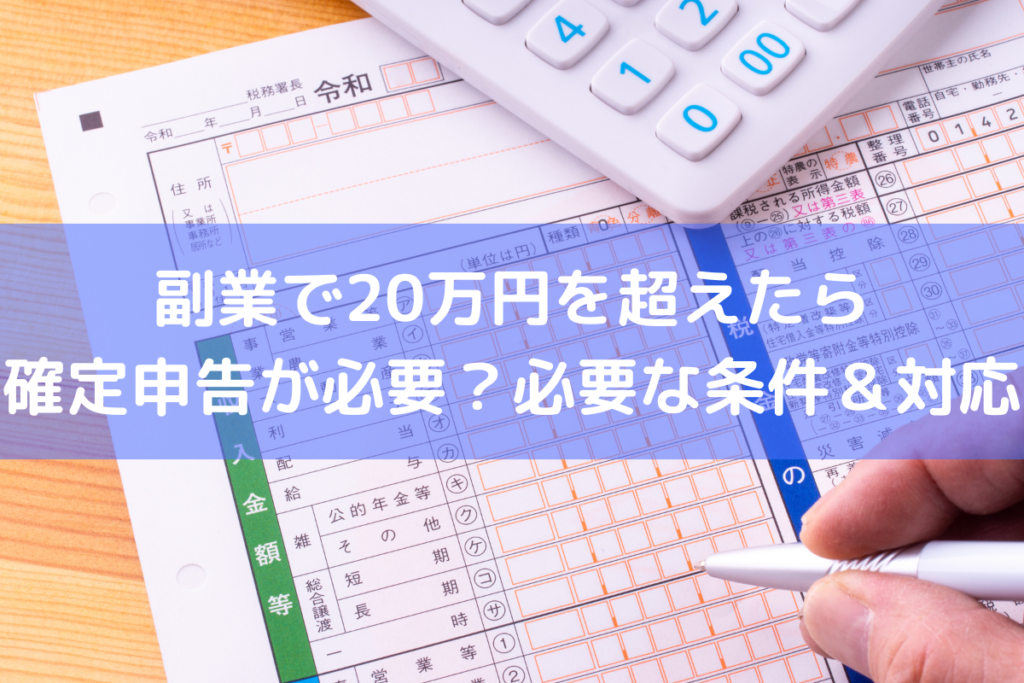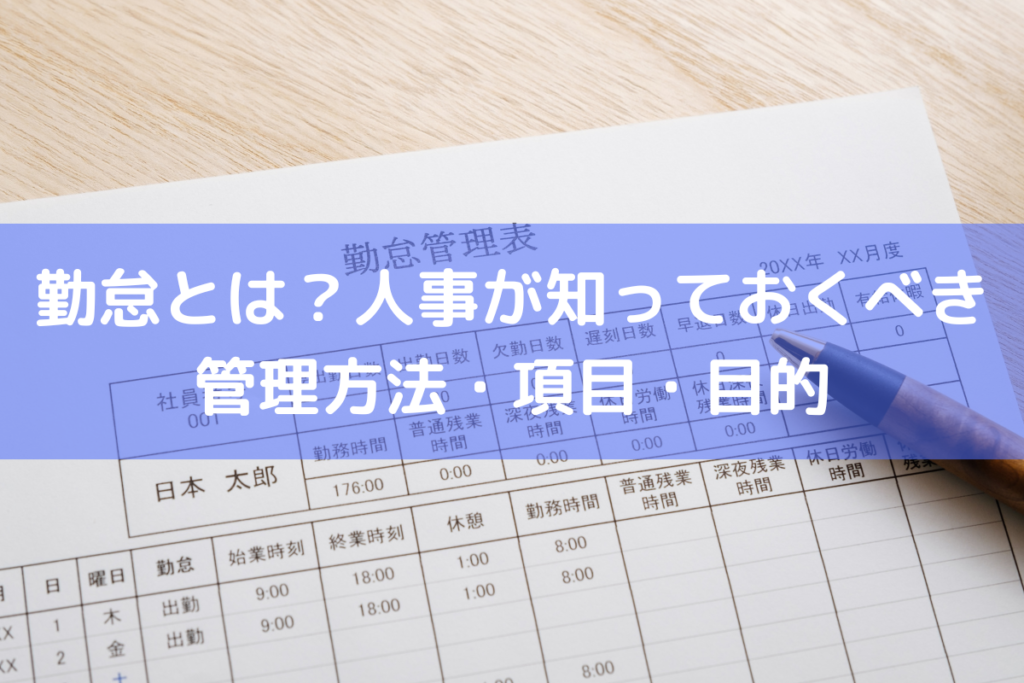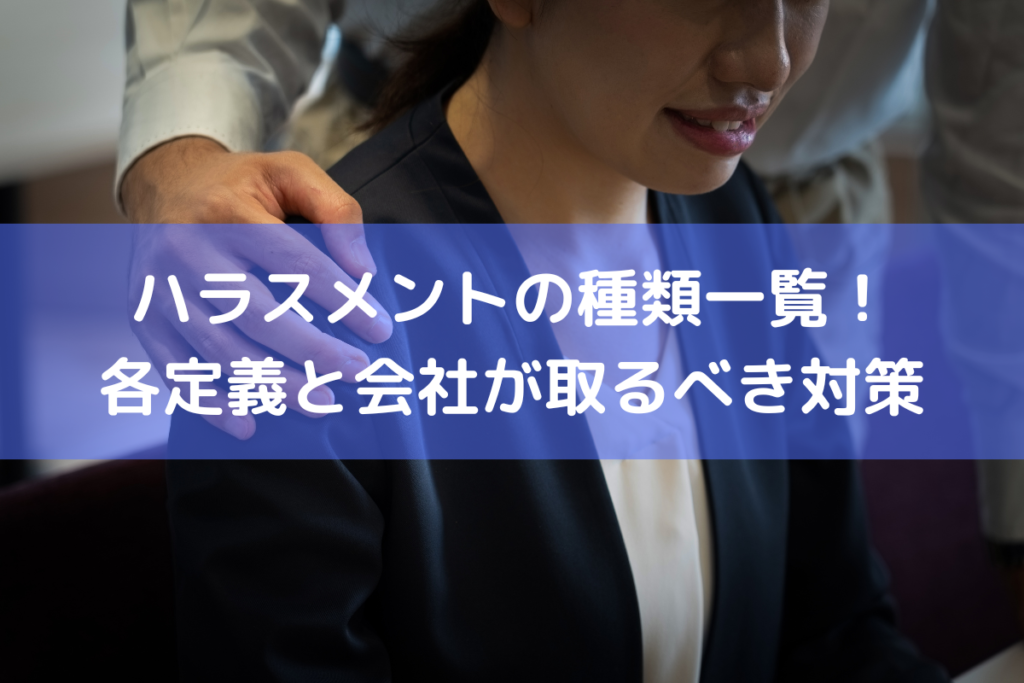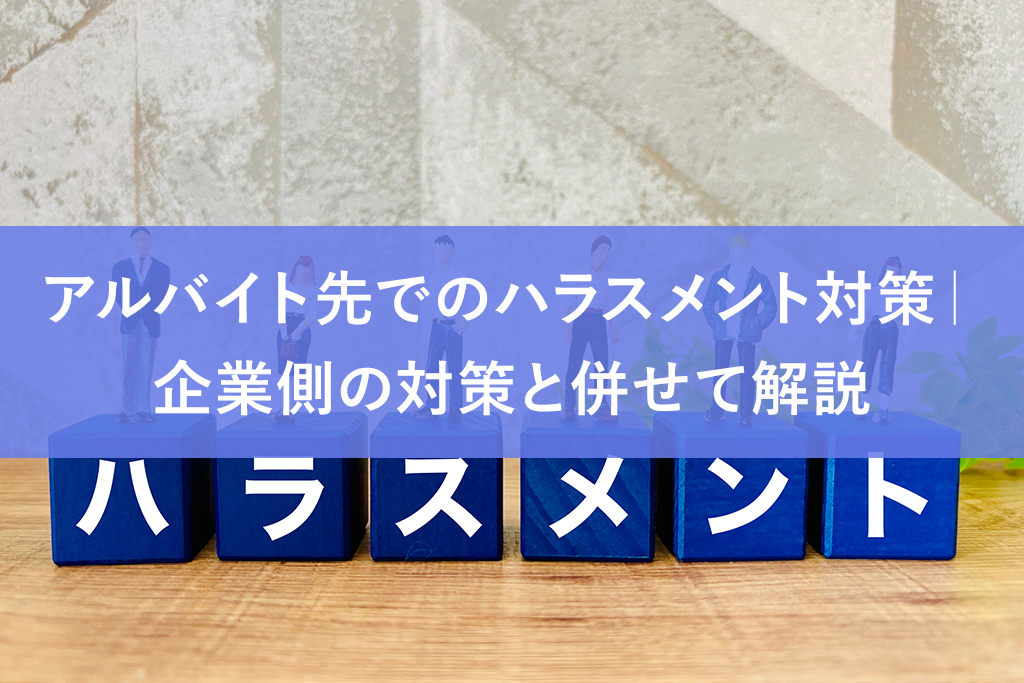
アルバイト先でのハラスメントは、誰にでも起こりうる問題です。「これはハラスメントなのではないか?」と悩んでいる方や、店長・オーナーとして対策に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。ハラスメントを防ぐためには、 まずハラスメントに関する知識を身に付けることが大切です。
この記事では、ハラスメントの種類や企業の防止対策、被害を受けた際の対処法などについて解説します。
アルバイトにおけるハラスメントの種類

ハラスメントと一言でいっても、その種類はさまざまです。ここでは、アルバイト先で遭遇する可能性のあるおもなハラスメントについて解説します。
パワーハラスメント(パワハラ)
パワハラは、職場での優位な立場や人間関係を利用し、適正な範囲を超えた言動によって精神的・身体的苦痛を与える行為です。厚生労働省は、パワハラを次の6つに分類しています。
・身体的な攻撃(暴行・傷害)
・精神的な攻撃(脅迫・侮辱)
・人間関係からの切り離し(無視・隔離)
・過大な要求(達成困難な業務の強要)
・過小な要求(能力に見合わない単純作業のみを命じる)
・個の侵害(私的なことへの過度な干渉)
これらはアルバイト先でも発生しやすく、被害を受けた場合、また被害の報告が寄せられた場合は早めの対応が重要です。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
セクハラは、労働者の意に反する性的な言動によって不快な思いをさせたり、就業環境を害したりする行為です。「対価型」と「環境型」の2種類に分けられます。
| 対価型:性的な言動に対して拒否・抵抗をしたことによって、解雇や降格などの不利益を受けるケースを指します。 環境型:性的な言動そのものによって職場環境が不快になり、働きづらくなるものです。 |
どちらもアルバイト先での被害は少なくありません。
モラルハラスメント(モラハラ)
モラハラは、言葉や態度によって相手を精神的に追い詰め、苦痛を与える行為です。パワハラが、職場での優位性を利用した行為であるのに対し、モラハラは必ずしも上下関係を前提としません。
例えば、無視や陰口、過剰な叱責などが該当します。陰湿で周囲が気付きにくいケースも多く、被害者が孤立しやすい点が特徴です。
ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
ジェンハラは、性別に基づく固定観念や偏見によって相手に不快感や不利益を与える行為です。「男のくせに」「女のくせに」といった発言・思想をはじめ、性別による役割分担の押しつけが該当します。
セクハラとの違いは、性的な言動に限らず、性別に関する固定観念に基づいた差別的扱いである点です。性自認や性的指向に関する偏見も含まれ、近年はLGBTQ+に関するハラスメントも問題視されています。
カスタマーハラスメント(カスハラ)
カスハラは、顧客などの第三者から受ける不当な言動や嫌がらせ行為です。特にサービス業のアルバイトは、顧客と直接関わる機会が多いため、被害に遭いやすい傾向にあります。
理不尽なクレームや暴言、SNSでの誹謗中傷などもカスハラに含まれ、企業側も従業員を守るための対策が求められます。
企業のアルバイトに対するハラスメント防止対策

企業は、アルバイトを含むすべての労働者に対して、ハラスメント防止のための具体的な対策を講じる法的義務があります。ここでは、企業が実施すべき主要な対策について見ていきましょう。
パワハラ防止法の概要と企業の義務
2020年6月に施行された「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」により、企業はパワハラ防止措置の実施が義務付けられました。大企業は2020年6月から、中小企業も2022年4月から対象となっています。
企業が果たすべきおもな義務は、次の4つです。
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・企業の方針の明確化およびその周知・啓発
・職場におけるセクシュアルハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
・相談者・行為者のプライバシー保護と不利益な取扱いの禁止
パワハラ防止法には、明確な罰則規定は設けられていません。しかし、これらを怠ると、厚生労働省からの是正勧告がなされ、応じなかった場合には企業名が公表されます。
アルバイトも対象となる相談窓口の設置
企業は、ハラスメントに関する相談窓口を設置し、アルバイトを含むすべての労働者が利用できるようにすることが義務付けられています。相談窓口の連絡先や利用方法は、就業規則や社内掲示などで明確に周知しましょう。
相談者が不利益な扱いを受けないことやプライバシーが守られることも明示し、安心して相談できる体制を整えることが重要です。
企業の方針明確化と周知・啓発活動
企業は、ハラスメント防止に関する方針を明確にし、アルバイトを含むすべての労働者に周知・啓発する必要があります。具体的な方針の内容は、次のとおりです。
・職場でのハラスメントの内容
・ハラスメントを行なってはならない旨
・ハラスメントを行なった者に対して厳正に対処する旨
・対処の内容
など
これらを就業規則への記載だけでなく、社内報、パンフレット、社内ホームページなどを活用して広く周知します。定期的な研修や説明会も有効です。
ハラスメント防止規程の整備と就業規則への反映
ハラスメント防止のためには、就業規則やハラスメント防止規程を整備し、明確なルールを示すことが不可欠です。規程の作成方法には、就業規則の一部として定める方法と、委任規程を設けて別途詳細を定める方法があります。
また、規程を新設・改定した場合は、「就業規則変更届」と「労働者の過半数の代表者の意見書」を労働基準監督署に届け出なければなりません。
管理職への教育
管理職は、部下の指導や評価を行なう立場にあるため、無意識のうちにハラスメントを行なってしまうリスクがあります。そのため、まずは管理者向けのハラスメント研修を実施することが重要です。
この研修では、ハラスメントの定義や基礎知識、ハラスメントリスクとその対応の意義などを学べるようにしましょう。座学だけでなく、ロールプレイングやケーススタディを通じて、受け手の立場を理解することも大切です。
ハラスメント発生時の対応フローの確立
ハラスメントが発生した場合、企業は迅速かつ適切な対応が求められます。一般的な対応フローは次のとおりです。
- 相談や苦情の受け付け
- 事実関係の確認
- ハラスメントの有無の判断と調査報告書の作成
- 被害者への配慮措置と加害者への処分などの措置
- 再発防止策の実施
初動対応の遅れや不適切な対応は、さらなるトラブルや企業の責任拡大につながりかねません。そのため、事前のマニュアル化や担当者教育が重要です。
アルバイトがハラスメントを受けた場合の対処法

アルバイトの立場でも、心身の健康や権利を守るうえで、適切な対処法を知っておくことが大切です。ここでは、ハラスメント被害にあった際の具体的な対処法について見ていきましょう。
ハラスメントの事実を記録する
ハラスメントを受けた際は、被害にあった日時や場所、加害者の言動、その場に居合わせた第三者など、できる限り詳細な内容を記録します。メールやメッセージのやり取り、録音なども証拠として役立ちます。
感情的な表現は避け、客観的な事実を時系列で整理することが重要です。これらの記録は、のちに社内相談窓口や公的機関に相談する際に、証拠となります。
社内の相談窓口への相談
2022年4月以降、すべての企業にハラスメント相談窓口の設置が義務付けられています。アルバイトでもこの窓口を利用でき、相談内容は守秘義務によって保護されるため、相談を検討するとよいでしょう。
相談者が不利益な扱いを受けることは法律で禁じられているため、安心して相談できます。
労働局・労働監督基準署の総合労働相談コーナーの活用
社内での解決が難しい場合や相談しづらい場合には、外部の相談窓口として労働局・労働監督基準署の総合労働相談コーナーも利用できます。ここでは、学生や就活生も含め、いじめや嫌がらせ、パワハラなど幅広い問題について、無料で相談可能です。
夜間や土日も対応している「労働条件相談ほっとライン」という窓口もあります。
法テラスなど無料法律相談の利用
ハラスメント問題が深刻な場合や法的対応が必要な場合は、法テラスなどの無料法律相談サービスの利用も検討しましょう。法テラスでは、要件を満たせば無料で弁護士や司法書士に相談できます。
相談は、法テラスの事務所のほか、電話やオンラインでも受け付けています。専門家の助言により、損害賠償請求や法的措置など、より踏み込んだ対応策を知ることができます。
アルバイトが知っておくべきハラスメント対策制度

アルバイトも正社員と同様に、法的に保護される権利があります。ここでは、ハラスメント被害にあった際に活用できる制度について解説します。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
2022年4月以降すべての企業は、業務上必要な範囲を超えた言動の禁止が明文化され、企業には相談窓口の設置や再発防止策の実施が義務付けられています。
アルバイトを含む全従業員が対象で、違反企業には厚生労働省からの指導が入るケースもあります。アルバイトであっても知っておくべき法律の一つです。
男女雇用機会均等法によるセクハラ防止
男女雇用均等法のなかでも職場におけるセクハラ対策として、企業に対して雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられています。
具体的には、セクハラ防止策の整備と相談体制の構築が企業に義務付けられており、「対価型」「環境型」の両方のセクハラが対象です。もちろんアルバイトも対象であるため、この法律による保護を受ける権利があります。
アルバイトの法的権利と保護制度
アルバイトやパートタイム労働者であっても、労働基準法や労働契約法などにより正社員と同様の法的保護を受ける権利があります。例えば、労働基準法第15条では、時給や勤務時間などの労働条件明示が義務付けられています。
アルバイトであっても、基本的な労働条件が保証されることを覚えておきましょう。
紛争解決援助制度(ハラスメント調停制度)
紛争解決援助制度(ハラスメント調停制度)は、各都道府県労働局が無料で提供する紛争解決制度です。当事者間でハラスメントの問題を解決できない場合には、この制度を利用することができます。
ただし、労働者と企業との間での問題が対象で、労働者同士のトラブルは対象外であることに注意しましょう。
アルバイトでも無料で利用可能です。
労働基準監督署への相談・申告
労働基準監督署は、労働基準法などの労働法令に違反する企業に対して、是正指導を行なう行政機関です。ハラスメントが労働条件の悪化や、長時間労働の強制などにつながっている場合は、相談・申告できます。
前章で紹介した証拠となる勤務記録やメールの写しを持参すると、より具体的な助言が得られるため、記録しておくことを忘れないようにしましょう。
「うっかりハラスメント」に要注意-「バイトルトーク」で事前防止
職場でのハラスメントは、意図せず発生する「うっかりハラスメント」にも注意が必要です。特に、個人アカウントのチャットツールやSNSを業務連絡に使用すると、プライベートとの境界が曖昧になり、「プライベートな時間に仕事の連絡が来る」「連絡先交換の強制や強要」といったハラスメントにつながりかねません。
ディップ株式会社、株式会社アイリッジが2024年に行なった調査では、アルバイトの42%、店長の50%が個人SNSでの業務コミュニケーションを問題視しているとわかりました。
そこでおすすめなのが、アルバイト現場に特化したコミュニケーションツール「バイトルトーク」です。アルバイトとのコミュニケーションに利用できるチャット機能やシフト調整機能はもちろんのこと、NGワード検知機能や本部への通報機能など、ハラスメント対策機能も備わっています。
まとめ
アルバイト先でのハラスメントは、誰にとっても身近な問題です。企業には、防止策の整備や相談窓口の設置が義務付けられており、アルバイトも正社員と同様に法的保護を受ける権利があります。
アルバイトを管理する側としても、無意識のうちに加害者となるリスクもあるため、日頃から正しい知識と適切なコミュニケーションを意識しましょう。
バイトルトークは、煩雑なコミュニケーションやシフト管理を効率化し、労働環境の改善を実現するサービスです。ハラスメント対策としても活用できるため、「バイトルトーク」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。